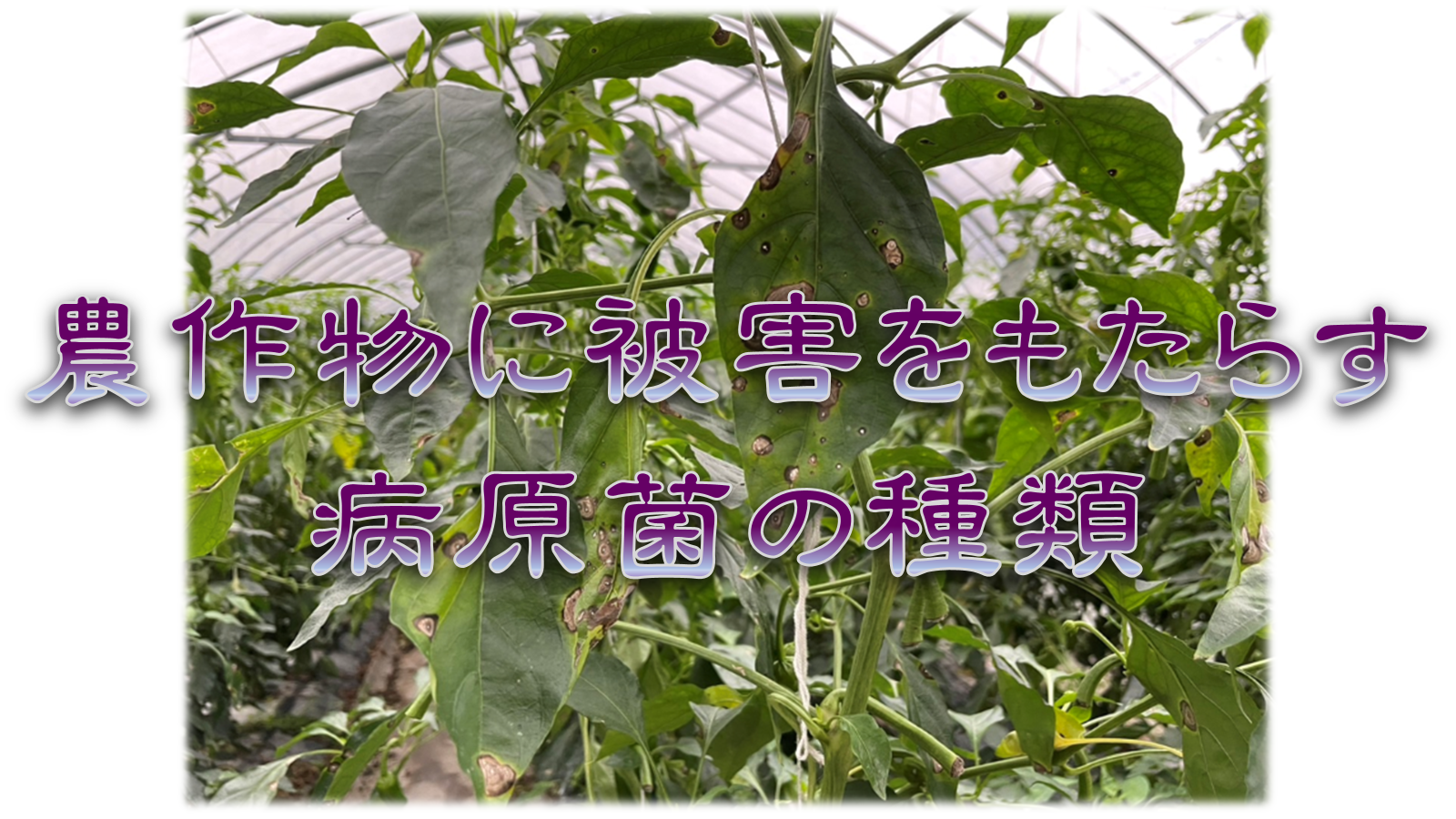
病原菌は肉眼では観察することができないため、農作物の茎や葉、果実にあらわれた被害症状を見て判断しなければなりません。
また、病気のように見えても、病原菌以外の要因によって農作物に被害が起きる場合もあります。
病原菌の種類
カビ(糸状菌)
作物の病気の約8割はカビが原因によるものと言われており、灰色カビ病、菌核病、うどんこ病、立枯れ病、白絹病、黒星病、べと病、いもち病、炭疽(たんそ)病などがあります。
農作物の萎凋や斑点、落葉、壊死など、症状は多岐にわたります。
カビは植物に付着すると、植物の体内に菌糸を伸ばして侵入し、やがて胞子を形成して飛ばし新たな植物について発芽をします。
このようにして次々と生息の分布を広げていきます。
他の病原菌もそうですが、カビは高温多湿の環境を好みます。
風に吹かれて胞子を飛ばすカビもあれば、水中を移動するカビもあり、雨や水やりによる泥はねで感染することもあります。
細菌(バクテリア)
軟腐病、斑点細菌病、青枯病、根頭がんしゅ病などの病気があります。
細菌による病気の被害症状は斑点、こぶ、立枯れ、腐敗などがあり、初期の症状は上記のカビの病気と似ており区別できないことがあります。
細菌は顕微鏡でなければ見分けられないほど非常に小さい単細胞微生物です。
バクテリアとも呼ばれ、細胞分裂によって増殖し、細菌の増殖するスピードは速く、植物が感染すると被害が広がりやすく厄介な病気です。
多くの細菌が水中を移動でき、土中の病原菌が水で移動し、新たな植物の根の傷口に侵入して増殖したり、感染した前作の残渣(ざんさ)や根の周囲の土壌で生息して伝染源となります。
ウイルス
ウイルス病、モザイク病、黄化えそ病などがあり、ウイルスは病害虫の代表アブラムシやアザミウマが媒介し運んできます。
農作物全体の萎縮、黄化、葉のモザイク、斑点などの症状があらわれます。
ウイルスは細菌よりもさらに小さく、電子顕微鏡でなければ観察できないほどです。
人間の場合は空気中に漂うウイルスから感染することがありますが、植物の場合は空気感染ではなく他の生物が運んでくることで感染します。ウイルスを媒介するのはアブラムシやアザミウマなどの昆虫が多いです。
こうして運ばれたウイルスは生物の生きた細胞に入り込んで自分のコピーを作り増殖します。
菌類や細菌と同様に病原体として扱われますが、遺伝子とタンパク質の殻という単純な構造で細胞壁がないことや自分の力では増殖できないことなどから、生物としては分類されていません。
ウイルスによる病害は農薬による防除ができないため、感染した場合は早めに取り除き、圃場外に廃棄したり焼却処分などで適切に処分することが重要です。
発生要因
土壌伝染
土壌中にいる病原体が植物の根や地下茎、塊茎などから侵入するなどして感染します。
土壌中の病原体は、長期間生き残ることができ、土壌の除菌や対策が困難であることが特徴です。
同じ土壌で同じ作物を作り続けていると、その作物を好む病原菌の密度が上がり、連作障害を起こす原因となります。
対処方法
- 土壌消毒
- 薬剤消毒…土壌消毒剤は種類が多く、薬剤によって適用が異なるため、目的に応じて選定する必要があります。土壌に残留すれば薬害発生の原因になりますので注意が必要です。
- 太陽熱消毒(蒸し込み)…太陽の放射熱で土壌の地温を上げ、50℃~60℃の高温に状態にすることで熱消毒することです。
- 土壌還元消毒…米ぬか・ふすま・糖蜜などの有機物を散布し耕起後土壌を水で満たし、さらに太陽熱で加熱を促しながら消毒します。
- 熱蒸気消毒…ボイラーなど専用の設備で作った高温の水蒸気を、パイプやホースなどを通して圃場(ほじょう)に流し込むという方法です。
- 太陽熱消毒(蒸し込み)…太陽の放射熱で土壌の地温を上げ、50℃~60℃の高温に状態にすることで熱消毒することです。
- 耕種的防除を取り入れる
- 抵抗性品種…もともと病気になりづらい抵抗性を有する品種が育成され、実用化されています。
- 台木…病原菌に抵抗性を持つ作物の根と根本の部分を活用し、その上に他の品種を繋げて接ぎ木栽培する技術のことです。
- 圃場衛生…前作の残渣物や圃場の雑草には病原菌が生息している恐れがあるので、それらを取り除き、圃場の整備を行うことが圃場衛生です。
- 輪作… 同一耕地に異なる種類の作物を交互に栽培することを輪作と言い、輪作を行うことで病原菌の寡占化を抑制します。
- 有機物施用や土壌改良…土壌に有機物を施用し微生物を活発化させます。土壌改良を行うことで化学性や物理性が改善され、病害虫に対する抵抗力も増大します。
- 環境管理…多くの病害は高温多湿条件で発生が助長されます。過繁茂や過度のかん水を避け、適宜換気を行いましょう。
- 雨除け栽培・袋かけ栽培…雨除け栽培は被覆を行ない雨がかからないようにして作物を栽培する方法で、袋掛け栽培は果実などに直接袋をかけて害虫の接触を防ぐ方法です。
- 台木…病原菌に抵抗性を持つ作物の根と根本の部分を活用し、その上に他の品種を繋げて接ぎ木栽培する技術のことです。
空気伝染(風媒伝染)
主にカビの胞子などが風により飛散し、植物に付着して感染します。
胞子は非常に小さく、ネットの網目や開口部を容易に通過するため、物理的に空気伝染を防ぐのは不可能です。
対処方法
- 農薬の散布
- 殺菌剤の予防的な散布、病斑が見つかった場合は治療効果のある薬剤の散布を行いましょう。
水媒伝染
雨や灌漑水、水たまりなどに存在する病原体が水の流れで運ばれ直接植物の気孔、水孔、傷口などに付着することで伝染するのが水媒伝染です。
対処方法
- 排水管理
- 雨水が侵入しない、かん水後に水が溜まらないなど圃場の水はけや風通しを良くし、過湿にならないように対策を行いましょう。
- マルチや敷き藁
- 灌水や雨による泥はねをしないようにマルチや敷き藁で覆いましょう。
- 薬剤散布
- 特に台風時や梅雨など雨期の前後に予防散布を行いましょう。
種子伝染
種子や種芋の表面や内部に付着した病原体が発芽後に増殖します。
種苗会社が販売する種であれば、きちんと管理されていたり種子消毒がされており種子伝染のリスクは少ないですが、自家採種(増殖)した種は注意が必要です。
対処方法
- 熱処理
- お湯や蒸気を利用して種子を一定温度で消毒する方法です。
- 薬剤消毒
- 薬剤を使用し種子の表面についた細菌や糸状菌を死滅させ、種子の発芽率と生育率を向上させます。
虫媒伝染
アブラムシやアザミウマ、コナジラミといった害虫やダニ、土壌線虫や菌類などにより運ばれ伝染します。
対処方法
- 媒介する昆虫の駆除
- ハウス等であれば防虫ネットを使用し害虫の侵入を阻止したり、農薬の散布、除草を行いましょう。
- 病害抵抗性品種の作付け
- 特定の病害虫やウイルスに対する抵抗性が強い品種を栽培することで作物の被害を防ぎ、収穫量を維持することができます。
接触伝染
芽かきや摘果などの作業中に病害に感染した農作物から病原体が手や農業器具などに付着し、そのまま他の農作物に作業を行うことで汁液などを介して伝染します。
対処方法
- 資材や器具、手指の消毒
- 使用した後の資材や器具は消毒を行い、手もこまめに洗いましょう。
- 作業を分ける
- 発病している作物と健全な作物の作業を分けるなどして伝染を防ぎます。
- 病害が発生している作物を早期発見することで接触伝染の被害を抑えることができます。
非感染性の病気
栄養素の過不足、適切ではない温度や湿度、光、散布農薬による薬害などが原因で起こり、生理障害と言われます。
生理障害の症状は病気と区別がつきにくい事が多いので、作物の状況をよく観察してみましょう。
関連記事
Youtube動画を見る



